愛しい貴方の姿は今日もなく、残されたのは置き手紙。貴方の行き先を告げる標。
それを頼りに、湖へ。律儀に置き手紙を残しこそするが、行き先はたいていここだ。
虫や鳥の声すらない静かな空気。あるのは水の流れる音ばかり。
穏やかな日差しが差し込む湖畔の木陰に彼はいた。
青々とした葉を茂らせる樹木にもたれかかり、腰掛けている。近づいて顔を見てみれば眠っているようだった。
あまりにも心地よさそうに眠っているものだから、声をかけるにも気が引けてしまう。
……見れば見るほど美しい。木漏れ日を受けて静かに輝く額の青い鱗。霜が降りたような白色の睫毛、一の字に結ばれた唇、氷のように澄んだ薄色の髪、透明感のある肌。呼吸するたび穏やかに上下する胸。身に纏う衣もまた白色で、ここが木陰でなければ眩いくらいだっただろう。本当にこの人は、白が似合う。
眺めているとふと気がつく。
これほどに毎日見つめているものを僕はほとんど知らないのだと。
手を握ることすら稀なのに、こんな尊いお顔を触れられるわけがない。
僕に触れようとするときも、決まって貴方は手を伸ばすのをやめてしまうから。本当は触れられたくないのではないかと何度思ったことか。
毎度のように許可を求めるのもきっと煩わしいだろうと、我慢ばかりを覚えた。
本当は、もっと貴方に触れていたい。もっと貴方を知りたい。僕の目は貴方を知っていても、手はほとんど知らない。目をつむって触れていても鮮明に描けるくらいに、貴方を知りたい。
なんて、口にすれば嫌われてしまうかもしれないから。だから我慢しているのに。
それなのに貴方はこれほどに無防備で。
触れれば届く距離に知りたかった全てが存在していた。
ああ、どうかいっそ目を覚ましてくれれば。そうしたら僕の過ちを止めてもらえるのに。
結局、自制心の敗れた僕は手を伸ばしていた。
滑る額の鱗。凛々しい眉。眉骨を伝い、閉じた瞼へ。本人が思っているよりも長い睫毛。通った鼻筋。……少し乾いた唇。
いつもすぐ目の前にあった『知らない』は容易く僕に知られてしまった。指を離してもなお触れた感触の余韻は残り続けて、僅かな瞬間はまるで永遠のように思えた。
指先の感触が全身になったかのように、僕の全ては貴方の感覚で満たされていた。
収まることのない心臓の高鳴り。はじめは見ているだけでよかったのに、触れてしまえばより深く知りたいと望んでしまう。
いっそのこと、貴方の全てを暴いてしまえば。そうしてしまえば、貴方は素直に嫌だと言ってくださるのでしょうか。
……いけない。冷静に、冷静にならなければ。
ああ、乾燥した唇に軟膏を塗らせてもらえればいいのに。
僕が数秒前の永遠に思いを馳せていると、眼前のそれは僕をじっと見ていた。白色に近い、薄らと青みがかった瞳。針のような瞳孔が静かにこちらを見据えていた。
「かお、何かついてた……?」
眼光の鋭さとは対照的に困惑した声色。
慌てて首を振って否定すれば「そう」の一言で再びまぶたを閉じてしまった。
邪な考えばかりが浮かぶ前に、彼の隣に腰を下ろし同じように目を閉じる。
そよぐ風が心地良い。風がこの心のざわめきも振り払ってくれることを祈り、樹木に体を預けた。
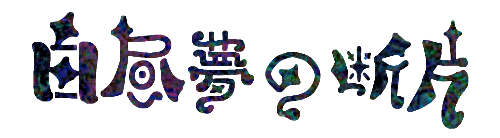
※コメントは最大5文字、5回まで送信できます