壁紙のダマスク模様は小さな生き物の集合体が息づくように蠢いていた。平らなはずの床はうねり覚束ない足取りに絡んでくる。
壁面に手を這わせれば微細な襞が触れるような感覚。数秒後には壁の存在すら感じない。
もたつく足にまとわりつく絨毯の感覚も同様に存在と非実在を繰り返す。何もかもが不愉快で吐き気を加速させた。皮肉にもその嘔吐感が鈍った歩を進ませた。
タイル張りの洗面所。兵隊のように規則正しく並んだはずのそれらは今や大小バラバラに全く統率を欠いた無秩序そのもの。薄暗い照明は不規則に明滅を繰り返し視界がちらつく。
そんなことはどうでもいい。込み上げてくるものを吐き出したくてに蛇口と鏡の前にいる。なのにシンクに両手をついて俯き、えづいても吐き気はそこに居座り続ける。それもそうだ。水一滴すらも口にしていないんだから吐くものなぞありはしない。
ふと顔を上げると鏡に映るものと目が合った。お前は誰だ?
俺じゃない、何者なのか認識できない。
視線を感じたはずの向こう側の眼差し。それは今や目など認識できないほど歪曲した鏡像と化していた。正体を掴もうと見つめるほどグチャグチャに、混ざり溶けゆく肉片の集合。
ますます気分が悪くなる。鏡を見ているんだから俺が映らないのはおかしい。間違っている。お前は誰だ。不愉快だ。人のいるべき場所にどうして我が物顔で居座っている。こんなのは俺じゃない。消え失せろ。
そう思ったときにはすでに遅く、衝動的に殴りつけた拳が鏡にヒビを入れていた。体の外殻に遠く感じた痛みが嘔吐感を遠ざける。
気分が良くてもう一度。ひと度舐めた飴の味が忘れられず食い尽くす子供のように、もう一度。もう一度を飴がなくなるまで何回も。
ザマアみろ。いなくなれ。お前が悪い。清々した。いつしか罵りは苛立ちよりも堪えきれない笑いへ変わっていた。ああ、気分が良くなってきた。
いつの間にか割れた鏡は俺への仕返しのつもりか、自らの断片を無数に突き刺していた。気まぐれな照明の光を必死に拾って、血に塗れた手の甲を着飾る愚かな宝石。もう鏡の中には誰もいなかった。しがみついていた吐き気も同様。ようやく眠れそうだ。
だから散らばった中のひときわ大きな煌きを手に取って首を撫でる。
ああ、やっぱり割らないほうがよかったかな。流れる血が見えない。まあいいか、もう死ぬんだし。流れる液体の暖かさと体の冷たさの比率は等号。なんて、考えてるうちにすべてが冷たくなってくる。崩れた比率の先に結ばれた回答は、死。
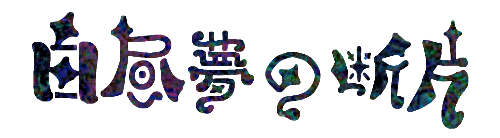
※コメントは最大5文字、5回まで送信できます